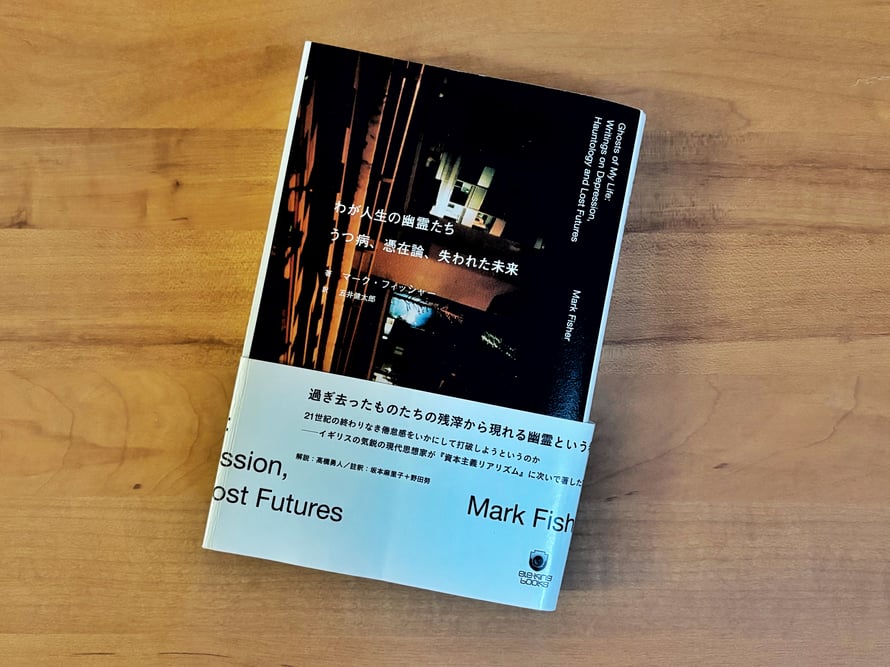
前置き
これはPARAでの幸村燕さんによるゼミ「加速主義とゼロ年代批評を横断する批評的縦断の実践」の課題で提出したエッセイである。
このゼミでわたしは加速主義やゼロ年代批評の著作に触れることができた。ゼミに提出したエッセイを5本ほど、このブログに載せようと思う。本稿は5つ目、つまり最後のエッセイである。前回までの4冊は課題図書としてあげられていたものから選ぶ形式だったが、最終回の5冊目の書籍は全く自由に選出することができた。わたしは4冊目に続きマーク・フィッシャーの著作を連続で取り上げることにしたのである。
すでにゼミの中で校正が一回入っているが、掲載するにあたり再度自分でも加筆修正した。また、当ブログでのレギュレーション (例:私→わたし と表記) に則って改訂している。また、本稿のページ表記 (p.XX) は マーク・フィッシャー 五井健太郎訳(2019) 『わが人生の幽霊たち――うつ病、憑在論、失われた未来』 Pヴァイン のページ数を示している。
前回のBook Reportでも触れたが、4月末にフィッシャーの主著 『資本主義リアリズム』 の増補版が発刊された。文学フリマ東京40の堀之内出版ブースにて買い求め、今、手元には通常版と増補版の2冊の 『資本主義リアリズム』 が揃っている。
過去に通読した際にはあまりピンとこなかった 『資本主義リアリズム』 であるが、最近になってようやく消化できる気がしている。いずれは 『資本主義リアリズム』 のBook Reportをこのブログに書かねばなるまい。
フィッシャーを読むには、語られているカルチャーへの造詣が必要不可欠である。当たり前のことではあるが、著述に登場する音楽やドラマや映画やアートを実際に鑑賞していれば理解が深まる。
本稿のエッセイで取り上げた 『わが人生の幽霊たち――うつ病、憑在論、失われた未来』 も同様だ。巻末の解説には「 『資本主義リアリズム』 がフィッシャーの政治・社会思想を写したものであるならば、『わが人生の幽霊たち』 はその文化論編として読むことができる(p.374)」と書かれている。この本は 『資本主義リアリズム』 よりさらに一層カルチャー色が強いもの、と言っていいだろう。
しかしカルチャーへの理解となると、フィッシャーが生きたイギリスとわたしのいる日本とではどうしても越えられないギャップがある。たとえば 「スマイリーの計略 —— 『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』」 の章(p.111〜)では、ジョン・ル・カレのスパイ小説を映像化したものについて語られているが、ストーリーについて論じているというよりは映画版とBBCドラマ版の演者の違いについて述べられているため、未だ完全に理解したとは言い切れない。2011年公開の映画版 『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ(邦題:裏切りのサーカス)』 を視聴することはできても、フィッシャーが絶賛している1979年のBBCドラマ版を観るのはなかなかにハードルが高い。
一方、音楽の話題となるとサブスクリプションの恩恵により音源に気軽にアクセスできる。以下のエッセイはフィッシャーが音楽について語った部分を取り上げている。ウォーリック大学のCCRU(サイバネティック文化研究ユニット) に参加していたフィッシャーは、そこでジャングルやドラムンベースを論じていた。フィッシャーの批評は音楽を抜きには語れない。
ポスト"後追い自殺"——マーク・フィッシャー『わが人生の幽霊たち——うつ病、憑在論、失われた未来』
マーク・フィッシャーの 『資本主義リアリズム』 そして 『ポスト資本主義の欲望』 の2冊を読み終えて、わたし自身がフィッシャーにとても惹かれていることに気づいた。フィッシャーの魅力は 「資本主義に代わるものなどありはしない」 という広くいきわたった信仰を自覚させることで、その強大な化け物を乗り越えようとする試みにあるのは間違いない。しかし、わたしは彼の語り自体よりも彼の文章の周囲に漂っている目に見えないもののほうに中毒性を感じている。具体的には、資本主義の興隆と比例して加速する世界的な鬱状態や、フィッシャーが引用している過去の作品たちの亡霊だ。フィッシャーの語りがある種のリリックであるならば、周囲に漂っているそれらはメロディーラインである。
この中毒性の謎を探るために、わたしは 『わが人生の幽霊たち——うつ病、憑在論、失われた未来』 を手に取った。本書は、思想のみならず、音楽、映画、アートと多岐にわたったフィッシャーの批評を、失われた未来、七〇年代の回帰、憑在論、場所の染み、という章に編纂したものである。冒頭では、1970年代から2000年代にかけて緩やかに未来が消去されていったことが綴られる。新自由主義的な資本主義における競争が決定的に新しいものを作り出すことを不可能にしていった。即ち、連帯や治安の破壊が「価値の定まったものや慣れしたしんだものへの渇望(p.34)」をもたらし、また、市場化による短期的成果の要求は「すでに成功したものに似た文化的な生産物(p.35)」を生み出したのだ。
過去のものからの引用は音楽では顕著である。本書のタイトルの元となるラフィッジ・クルーの「ゴースト・オブ・マイ・ライフ」(1993年 『Ghosts E.P.』 収録曲)とそのサンプリング元であるジャパンの 「ゴースト」(1980年 『Tin Drum』 収録曲)、そしてトリッキーの 「アフターマス」(1995年 『Maxinquaye』 収録曲)へと断片が流れ着いたことがフィッシャーによって語られていく。ジャパンのデヴィッド・シルヴィアンが 「手に箸を持ち、毛沢東のポスターが背後の壁から剥がれかかっているのをそのままにして、簡素な中国風の家のなかに座っている。(p.65)」 という 『Tin Drum』 のジャケットはオリエンタリズムの現れであり、さらにラフィッジ・クルーがゴールディという 「人種の入り混じった金歯の元グラフィティー・アーティスト(p.58)」 であること、トリッキーの出自もまた 「父はジャマイカ人で、祖母は白人(p.69)」 というものであることから、白人から見たプリミティブなものへの回帰が示されている。話題にされているのはジャングルという音楽ジャンルであり、それが持つ 「ダークなものの魅力(p.56)」 である。ダークサイド・ジャングルでは連帯や治安が破壊されており、人間や非人間がおたがいを密かに追跡しあっている。それはまさに資本主義社会そのものなのである。
このダークさは 「黒さ」 となってジョイ・ディヴィジョン論へと橋渡しされる。ジョイ・ディヴィジョンは1976年に結成されるも、1980年にフロントマンのイアン・カーティスが自殺したことで解散した。1979年の1stアルバム 『アンノウン・プレジャーズ』 は、今日では、ジャケットのアートワークが 「もっとも売れているインディ・ロックのTシャツ(p155 編註)」 となり、ネットミームとしても頻繁に登場している(1)。フィッシャーのいう 「黒さ」 とは 「黒人のポップ・ミュージック(p.98)」 のことであり、ジョイ・ディヴィジョンの音にはその影響があるという。しかし、その論は次第に1979〜80年の英国でおこった転換——即ち、社会民主主義的でフォーディズム的な産業的世界から新自由主義的で消費者的な情報科学的世界への変化——と結びつけられるカーティスの鬱状態に焦点があたっていき、「黒人のポップ・ミュージック(p.98)」 の 「黒さ」 は 「鬱のもつ黒さ(p.103)」 へとすり替わっていく。フィッシャーの議論の中で有色の黒が、いつの間にか無の空間の黒へと変化しているのである。この変遷は、実体ある社会の中に潜む実体のないもの、を読者に印象づける。本書の挿絵としてローラ・オールドフィード・フォードのドローイングが添えられているが、そこに見ることができるのは、工業化が進んだ郊外の高速道路の橋桁と雑草とフェンス、わずかに視界に入るグラフィティのタグ、そして描かれていない漂う幽霊である。これこそフィッシャーが魅せられたものであろう。
これがあまりにも魅力的なために、フィッシャーはイアン・カーティスの後追い自殺をしたのではないか、という疑いがわたしの中にある。未来が参照し続ける過去のある時期に魅せられ取り憑かれてしまったのではないか。しかしながら、そんな後追い自殺のループこそ抜け出すべきだろう。われわれは未来を予見することができない生き物、即ち常に過去を見ながら後ろ向きで進んでいる生き物である。過去に魅せられるのは何も特別なことではない。また新しい過去が眼前に積み上がり、そこにいつしか未知の快楽が紛れ込むこともあるだろう。フィッシャーが魅せられた 『アンノウン・プレジャーズ』 のジャケットをミームとして楽しむ現在こそがその証拠である。
注釈
(1)例として、
pic.twitter.com/v5g5Jql4mN など。
また 『Unknown Pleasures』 のジャケットを引用した商品をまとめた「Division of Pleasures」という作品集も発行されている。
https://utrecht.jp/collections/all/products/division-of-pleasures-vieceli-cremers
関連記事





コメントをお書きください