
前置き
このFRENZIEを立ち上げてから、PARAや浄土複合の講義に提出した課題ばかりあげているので、たまにはそういうものとは関係なく自分勝手に書いたものを載せようと思う。この前置きのあとに載せるものは、賞への応募なども全く念頭に置いていない、このブログのためだけに書いたものである。
自分は自分の裁量でできることが好きなのかもしれない。noteのようなプラットフォームもある時代に、わざわざ個人ブログをつくる理由はなんだろうと自問してみると、どうやら私は自分勝手にやりたいのだということに辿り着く。noteだって自由だといわれればそうなのだが、、、私は背景カラーからロゴまでいじりたいし、ページ階層を含む全体の構造やリンク、広告・アフィリエイトをどこに出すか、なども考えたりしたい。まるで路面店を持つような楽しさが個人ブログにはある(いや、路面店を持ったことはないのだが?)。個人ブログが路面店ならnoteは百貨店内テナントである。この微妙なちがいは伝わるだろうか、、、?
かんちがいされるといけないので補足するが、他者からのフィードバックはめちゃくちゃ欲しい。ライティング講義の最大の旨味は他者からフィードバックがもらえることである。自分の文章を最後まで読んでもらえることがレアな時代に、フィードバックはかなり価値がある。そのフィードバックへの受講料という考え方もできなくはない。受講期間が終わってしまえばフィードバックはもらえなくなる。
ならば、フィードバックをもらえるうちにその他者の目線を自分の中に芽生えさせることができれば良い。そうして、個人ブログの記事にも客観的な読みやすさが備わっていけば良いと思っているが、今の時点で果たして少しは変化しているだろうか。時にはブログのためだけに書いて変化を確認したほうが良さそうだ、というわけである。
久しぶりにブログの自由さに触れると、そこに甘えて長々と書いてしまった気もする。
銀座はやらかしているか——アナ・トーフにみる身体
銀座という街は、やらかしているのではないか。
やらかしている?なにを?
さかのぼること2021年、グッチとバレンシアガによる「ザ・ハッカー・プロジェクト」というコラボレーションがあった。銀座の地下ショーウィンドウにはオールドグッチのようなバッグが並ぶ。しかしよくみるとそのモノグラムはグッチの「GG」ではなくバレンシアガの「BB」であり、さらにグラフィティのタギングを思わせる文字で「THIS IS NOT A GUCCI BAG」と走り書きされている。
銀座松屋のショーウィンドウにもスプレー缶で書かれたような「GUCCI」という文字が大きく施されていた。当時の様子を撮影していなかったのでここに載せることはできないが、「ザ・ハッカー・プロジェクト」で検索すれば今でも画像が確認できる。
このタギング風の走り書きの表現は、グラフィティ・ライターのKIDULTの「ブランダライジング」を想起させるものであった。
「ブランダライジング」とは、ブランド+ヴァンダライズ(破壊行為)を意味する造語で、ラグジュアリーブランドのショーウィンドウにタギングするKIDULTの表現である。以下の動画のその様子が記録されている。
上の動画内では、マーク・ジェイコブスによるルイ・ヴィトンのモノグラム・グラフィティが非難されている。KIDULTの活動の根幹には資本主義の闇の部分、すなわち弱者に対する破壊行為、強奪、搾取等への憎悪があるが、彼の表現のスタイルだけを掠め取って、強者による金儲けの道具へと変換させるような行為は非難されるべきであろう。このことに対する嫌悪感は、前述の「ザ・ハッカー・プロジェクト」をみた一部の人にも沸いた感情である。
「ザ・ハッカー・プロジェクト」にまつわる一連のプロモーションを知ってから、私の中で銀座という街には「やらかしている」という印象がこびりつくようになった。
そのような理由から、銀座メゾンエルメスにあるギャラリーで展示をみる際には自分の中に妙な捻くれが生じている。エルメスといえば、グッチ、バレンシアガ、ルイ・ヴィトンと並び称されるラグジュアリーブランドである。やらかしている銀座とラグジュアリーブランドとアートの組み合わせときくと、どうしても斜に構えてしまうのだ。
具体的にはこのようなことだ。展示作品から資本主義批判的な文脈を嗅ぎ取るとそこに固執してしまいがちになる。「何をいっているんだ?ここは銀座で、エルメスの上階だぞ。見掛け倒しの資本主義批判ならやめてくれ。ただのポーズにしか感じられない。スタイルだけを掠め取った『ザ・ハッカー・プロジェクト』のことを省みることすらしていないのか」というわけである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
先日、銀座メゾンエルメスのギャラリーで「体を成す からだをなす——FRAC Grand Large 収蔵作品セレクション展」(会期終了)を鑑賞した。その時も上記のような捻くれた気持ちは根底にあった。だが、その気持ちに何らかの影響を与える作品に出会ったような気もしている。
その作品とはアナ・トーフによる映像作品《サイドショー》である。39分という長さにもかかわらずすべて鑑賞してしまった。

何を表現しているのか、正直、はじめはわからなかった。
スクリーンに映し出された画面は次のようなものである。全体に強烈な光が当たっており、その光はピンクから青、黄色から赤と変化を繰り返す。板のようなもので区切られた3つの出入口があり、そのうちのどこからか仮面舞踏会用に装ったような人間があらわれる。彼らは身体をつかい何かを表現したかと思うとまた出入口から奥へと消えてしまう。



そんなことが延々と繰り返される。鳥の被り物をした者や猫のような出で立ちの者もいる。なんなのか本当にわからなく、ゆえに不気味さも感じる。この作品が展示されている部屋に入るや否や「こわっ」とつぶやいてすぐ出て行った人もいた。
わからないなりにみていると、色のついた強烈な光のためか、画面にあらわれては去っていく人間の残像のようなものがみえはじめた。誰かの「こわっ」という感想につられて、なんだか心霊現象をみているような気分になってくる。
誘惑に負けて手に持っていた展覧会のハンドアウトを確認すると、そこには以下のような解説が記してあった。
ベルギー人アーティストのアナ・トーフは、ヴィデオ・インスタレーションで、キャバレーとサイレント映画に触発された演劇的なイリュージョンの視覚効果に挑んでいる。芸者、透明人間、鳥人間などがカラフルな光を浴びながら、スクリーンを練り歩く。《サイドショー》で、トーフは仮面舞踏や見せかけ、消失、死というテーマを探究する。その投影は社会的なメタファーとなっており、誰もが人工的に記号化された集団的演出の中でステレオタイプな役割を演じている。観客は、この見せかけの劇場に巻き込まれ、構築されたセットの中で自らの居場所を問うことになる。
これを読むと、作品のいわんとしていることが掴めてくる。登場するわけのわからない人物たちはそれぞれの社会的役割を演じているわたしたち自身をあらわしている。鳥人間は鳥らしく、猫人間は猫っぽく。みな一様に仮面を被っているのはその仮面が社会にみせている面ということだろう。仮面を取っても中が仮面だった人物が印象的だ。本当の自分なるものをさらけ出したようにみえても、社会という舞台にいる以上、みな仮面をつけているのである。仮面はわたしたちの皮膚そのもののように身体とわかちがたく結びついている。


そういったことを読み取りながらも問いが沸く。ハンドアウトを読む前のわたし自身がみてしまった残像のようなものはどのように解釈可能だろうか。色のついた強い光はキャバレーを表現しているといえるが、なぜキャバレーの光が必要だったのか。展覧会全体のタイトル「体を成す からだをなす」というテーマを考えると、映像内にあらわれている人間の身体がキュレーションテーマに沿っていると考えるのが素直と感じるが、トーフの作品にはもうひとつ、鑑賞者の身体ということが念頭にあったのではないだろうか。
色のついた強烈な光の中で一定時間止まった後に動きだすものをみると残像が生まれやすい。実際、《サイドショー》はカクカク動いていて人物の静止と動作が繰り返されており、残像がみえやすいように演出されているともいえる。残像をみてしまうというのは個人の感じ方ではなく、身体的な、生理現象に近いものである。みようとしているわけではなく、みえてしまうのだ。
このことは狙って演出されているのか。カラフルな光はキャバレーの雰囲気を出すためのものであり、カクカクした動きもサイレント映画を表現したかっただけかもしれない。考えすぎかと思ったが、会場内に参考資料として置かれていたトーフの『ECHOLALIA』内の論考を読むと、あながち考えすぎでもないと思った。そこにはトーフの別の作品《[...] STAIN [...]》についての批評があった。その批評および《[...] STAIN [...]》という作品を調べた限りでは、トーフは色つきガラスの色とその奥にみえるものの色とのちがいに意識的である。
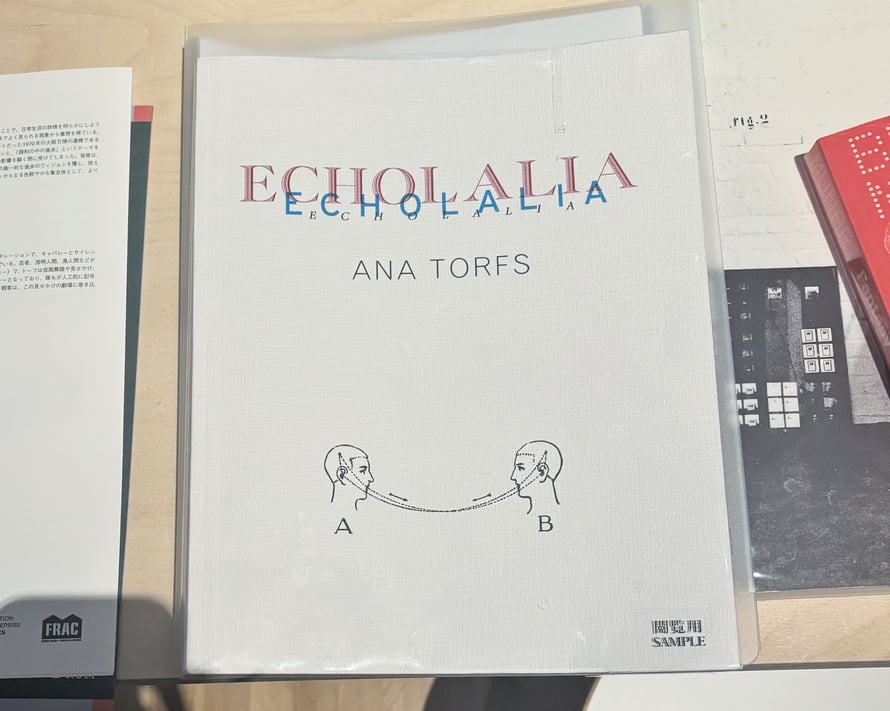
《[...] STAIN [...]》について軽く説明すると、この作品はコールタールなどの製造過程で生まれた合成染料20色のカラーガラスを用いたインスタレーションである。それぞれの色つきガラスは黒のフレームにはめられ、フレームの中には色の名前と、その色に染められた羽根の画像と、関連するイメージ画像がある。さらに音声で色の名前とイメージ画像のキャプションを人工的な声が読み上げる、というものだ。
わたしが注目したのは、色つきガラスと、その奥にある羽根の色との関係である。トーフの《[...] STAIN [...]》において、ある色をみたいと思ってひとつのフレームを覗き込んでも、その色つきガラスは透明であるために奥にある染められた羽根が目に入る。ガラスも羽根も、どちらも同じ色に染められているのに、色見本のような不透明で正確とされる色は把握できない。ガラスは透明であるし、そのガラス越しにみる羽根は色が2倍に重なったような状態なのである。件の批評においては、フレームの中をみる鑑賞者の視界が文字通り色づけされたことが論じられていた。
つまり、トーフの作品はわたしたちが意図せずにみてしまうものに注意を向けさせる。鑑賞者の目、鑑賞者の身体においてどうにもならない現象が加わることで完成する作品なのである。《[...] STAIN [...]》では色づけされてしまう視界であり、《サイドショー》ではみえてしまう残像が、作品の一要素として不可欠なのではないか。
この自動的に「みえてしまう」ということが、わたしの銀座に対する捻くれた気持ちに揺れをもたらした。残像がみえてしまうのは身体的に仕方のないことで、残像をみようとしているわけではない。ある種の生理現象だとすると、大事なのはその身体由来の現象を認識することなのではないか。銀座に対して、あるいはラグジュアリーブランドに対して「捻くれた気持ち」と自分で書くということは、捻くれてると自覚しているのである。事実、数年前に銀座でやらかしたのはバレンシアガとグッチであってエルメスは関係ない。ラグジュアリーブランドでくくってしまうというのは、主語が大きい状態だ。そして、ラグジュアリーブランドとアートとの結びつきすべてが、見せかけの資本主義批判である、ともいい切れないはずだ。だがこの捻くれた気持ちを「捻くれているから直さなきゃ」と思っても直らない。捻くれた見方こそがわたしにとっては「みえてしまう」ことなのである。
みえてしまうものをみないようにすると自分に無理が生じる。わざと目をそらしているような気持ちになる。みてみぬふりをしているような気持ちだ。わだかまりが残ってしまい、かえってそれにとらわれてしまう。
重要なのは「みえてしまう」ことを受け入れ、かつ、みえてしまうものは幻影である可能性を考慮することなのだ。
トーフの《サイドショー》において、身体的な構造の問題で残像がみえてしまうこと自体は真実である。「みえてしまう」ことを否定するのではなく、みえてしまうものが残像である可能性、つまり実体を伴わないものである可能性を考えたい。そのほうがものごとに素直に向き合えるのではないか。わずかな差のようにきこえるが、このちがいは大きい。
みえているものを疑いましょう、という訴えは珍しいものではなく、それをテーマにした作品も多くあるだろう。だが、それらを鑑賞したときのわたしの受け止め方は「自分の見方を直そう」というものであった。トーフの作品は、自分の見方そのものは直せない、という認識をもたらした。極端なことをいえば、自分が意識しただけで昆虫の視覚が手に入る、ということはないのだから、みえている対象のほうを盲信しないことが重要なのである。自分がみているものは幻影かもしれない、その意識はポスト・トゥルースの真逆をいく。フェイクニュースという概念が存在する今の時代に要請される意識なのかもしれない。
関連記事


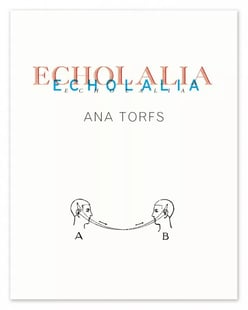

コメントをお書きください